とても頑張った後に、気が抜けてしまったり、無気力になったり、元気がなくなったり、体調が悪くなったり…
そんなときに、“燃え尽き症候群(バーンアウト)”は、よく聞く言葉ですよね。
「あの人、最近元気ないけど先日まですごく頑張ってたから燃え尽き症候群かな?」
こんな感じで気軽に使われる言葉でもあると思います。
ところが、燃え尽き症候群は危険な症状なのです。
<学生なら部活や文化祭、体育祭などで頑張った後に>
<社会人なら大きいプロジェクトや期待がかかった仕事の後に>
このような想定ができる燃え尽き症候群。
その影響は“その人のすべて”に及んでしまうのです。
つまり学生なら学校以外、社会人なら会社以外、すべての環境で症状が出てしまいます。
燃え尽き症候群の症状は?
燃え尽き症候群の症状は、大きく3つに分けられます。
【1】情緒的消耗感
⇒人付き合いで気を使うことに対して、心も体も非常に疲れるようになります。
【2】脱人格化
⇒情緒的消耗感の疲れから逃れるために、気を遣わ(遣え)なくなります。
【3】個人的達成感の低下
⇒情緒的消耗感と脱人格化が進み、達成感や使命感、やりがいなどが損なわれます。
この3つが相互に関連しあうことで、体調を崩したり、極端なやる気の低下、さらに厳しい状況になると、うつ病やその他の精神疾患に発展してしまう可能性もあります。
どんな人が燃え尽き症候群になるの?
燃え尽き症候群は、個人特性と環境特性でそれぞれ原因になるものがあります。
【個人の特性】
・20代~40代の若い世代
・仕事に熱心でひたむき、真面目
・理想が高い
・取り組むものへの経験値が少ない
などが挙げられます。
【環境の特性】
・仕事の拘束時間が長い
・目標が高すぎる
・上司からの期待が異常に高い
・仕事内容に対して評価や待遇が見合わない
・足並みをそろえるように強要される
などです。
燃え尽き症候群の予防策とは?
燃え尽き症候群の予防策をいくつかご紹介します。
・副交感神経の優位性を高める
=瞑想(めいそう)や筋弛緩法でリラックスする
・仕事の業務量を調節する
=仕事だけに執着しない
・仕事中の休憩や息抜きをする
=長い緊張感から解放させる
・好きなことをする
=自分だけの時間を作る
・旅行や遠出をしてみる
=いつもと違う時間の過ごし方をする
・実家に帰省してみる
=今と違う自分を思い出して気持ちを刺激する
個人的な特性を強制することは難しいはずですので、筆者自身は遠出をしたり、実家に帰省することを実践しています。
適度な環境変化は、普段の日常を見つめなおす機会にとても優れているのでおすすめです。

いかがでしたでしょうか?
燃え尽き症候群は誰でもなる可能性があり、なりやすい人は何度もなってしまうこともあります。
さらに悪化すると精神疾患まで進んでしまうことあるので注意が必要です。
「単なる仕事のやり過ぎだから適当に休めば大丈夫」「ストレスの蓄積だからストレス解消すれば大丈夫」などと甘くみていると危ないのです。
仕事熱心で頑張りすぎてしまう人は要注意。
もともと頑張りすぎてしまう、期待に応えるために、自分の昇進や昇格のために、いろいろな状況や理由はあると思います。
少しでも思い当たる節がある人は注意しましょう。
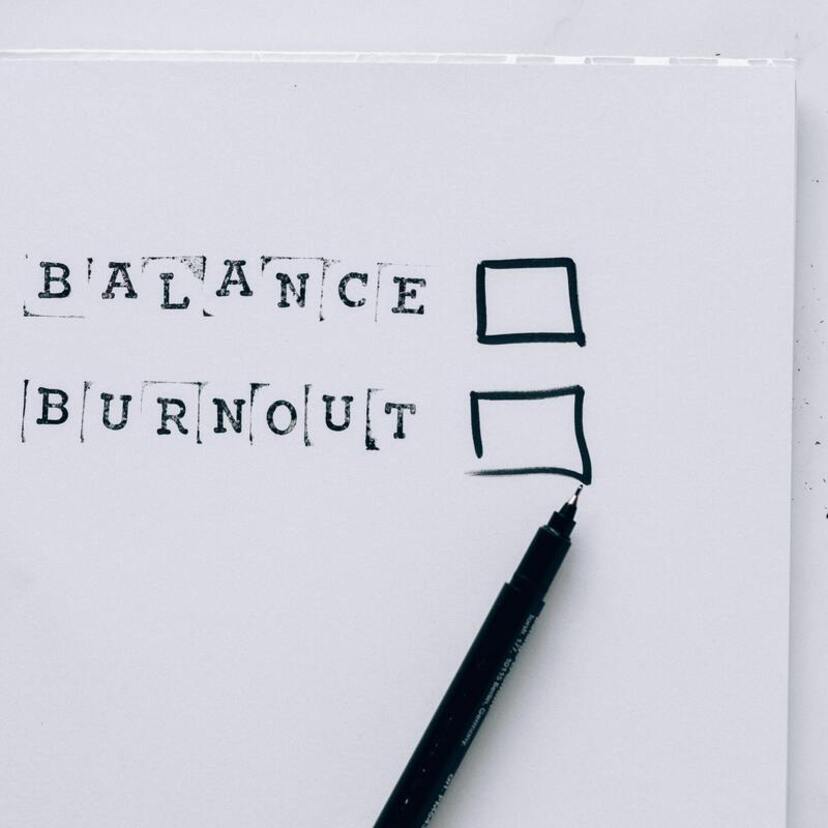
















神奈川県生まれ。心理カウンセラー・キャリアコンサルトの有資格者。うつ病 / パニック障害 / 適応障害 / 依存症 / などの精神疾患から仕事や日常的な悩みなどを幅広くカウンセリング活動を行う。社会問題から心理学関連、カウンセラー活動記録、研修・教育、など人や仕事に関わるジャンルでライティングを行う。趣味は、アニメ鑑賞、競馬、散歩。採用コンサルタント、就業ケアマネージャーとしても活動。